HaKaSe+(ハカセプラス)選抜学生として、博士学位の取得を目指して研究に励む、自然科学研究科電子情報科学専攻博士後期課程3年(取材当時)の小林 和樹さんに、博士後期課程の魅力や研究のやりがいについてお聞きしました。
博士後期課程に進学を決められたタイミングと、そのきっかけを教えてください。
進学を決めたのは学士課程4年のときです。博士前期課程までの進学は決めていたものの、修士号を取得して社会に出るか、さらに研究を続けるかを迷っていました。そのとき取り組んでいた卒業研究のテーマは、ダイヤモンドの結晶成長技術についてです。この研究が面白いと感じたこと、そして自身で開発したダイヤモンドを基板材料として、デバイスに応用したいという気持ちで大学院に進学し、5年間学ぶ決意を固めました。学士課程4年のときからの指導教員であるナノマテリアル研究所の德田規夫先生のもとで学びたいと感じたことも決め手になりました。
HaKaSe+ではどのような支援が受けられますか?
私は博士前期課程1年のときから5年間、HaKaSe+の中でも「ナノ精密医学・理工学卓越大学院プログラム(HaKaSe+ for WISE)」の支援をいただいています。経済的な支援に加えて、特に印象的だったのは「ラボローテーション」です。HaKaSe+ for WISEでは、医学系と理工学系の学生がそれぞれ互いの研究室を体験するもので、私は医学系の研究室を訪問しました。工学では既存の技術を組み合わせて新しいものを作る‟組み立て型“の発想が中心ですが、医学では未知の構造を一つ一つ解き明かす‟分解型”のアプローチが多く、研究の考え方の違いに大きな刺激を受けました。実際に、異分野の視点に触れることで、自分の研究をより広い視野で捉える力が養われたと感じています。
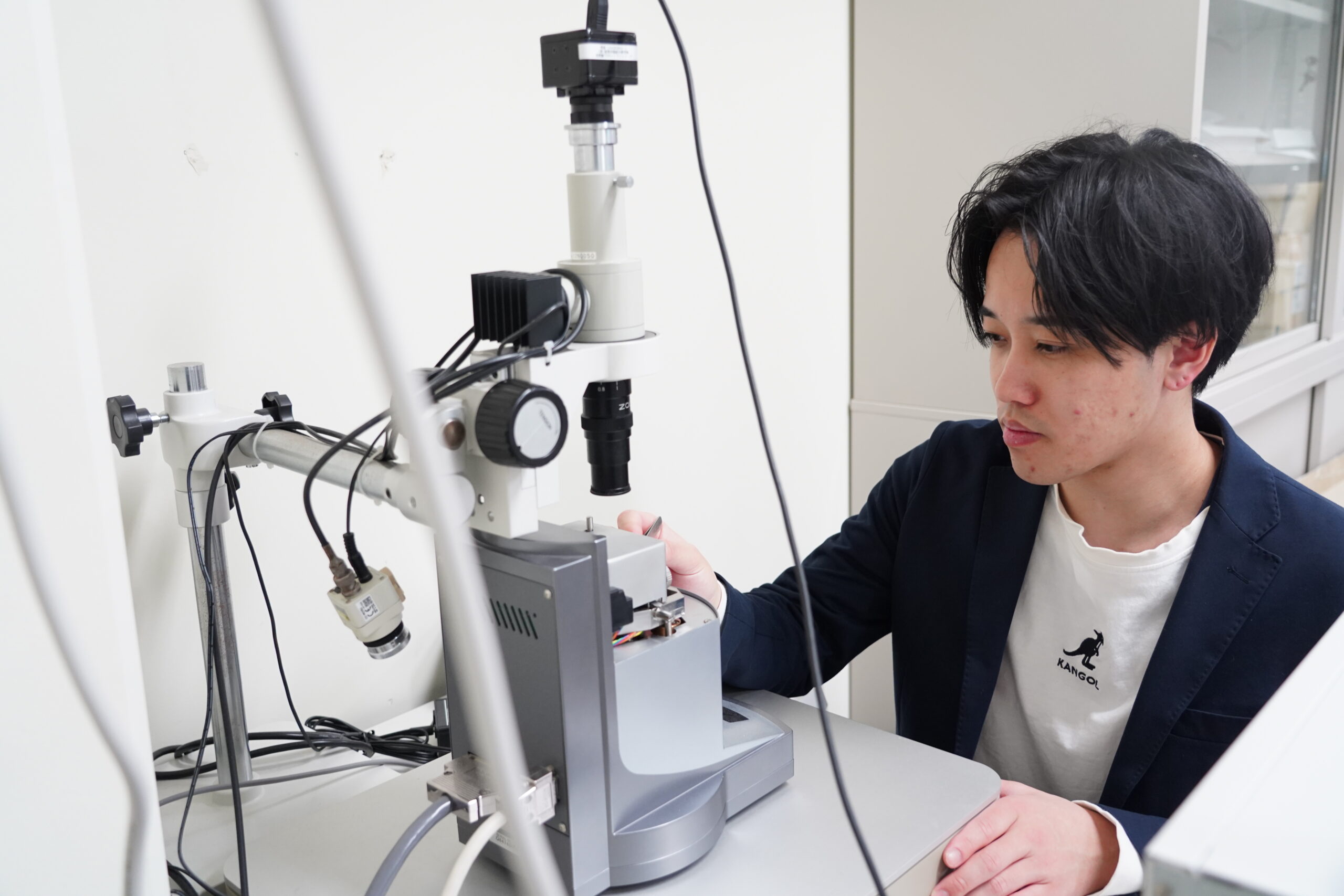
どのような研究をされているのですか?
私は、次世代の半導体材料として注目されている「ダイヤモンド」を使った半導体デバイスの研究をしています。特に、MOSFET(モスフェット)という電気の流れをコントロールするトランジスタをダイヤモンドで作製し、より高い性能を出すことが目標です。この研究では、ダイヤモンドと酸化膜という2つの材料の「接する面(界面)」を、原子レベルで平坦にすることに取り組んでいます。この界面が平坦であるほど、電気がスムーズに流れ、デバイスの性能が良くなるからです。現在広く使われているシリコンという素材には限界があり、より高性能な素材としてダイヤモンドが注目されています。電力の無駄を減らすことで、最終的には電力損失の低減やカーボンニュートラルといった社会課題の解決にも貢献できると考えています。
博士後期課程で身についたことがありましたら教えてください。
博士後期課程で最も身についたのは、「常識を疑い、自分の頭で深く考える力」です。論文や学会発表の内容をそのまま受け入れるのではなく、本当に正しいのかを自分で検証する姿勢が自然と身につきました。実際に、再現性を確認するために実験を行った際、既存の主張と異なる結果が出ることもあり、情報を鵜呑みにせず、自分の目で確かめることの大切さを実感しています。また、研究を進める中で生活リズムが不規則になることもありましたが、結果を出すために自分なりのペースや習慣を見つけ、パフォーマンスを維持する工夫もできるようになりました。こうした経験を通じて、柔軟な思考力と自己管理能力が養われたと感じています。
最後に将来の夢を聞かせてください。

将来の夢は、日本に世界的に競争力のあるラボグロウンダイヤモンド(研究室で製造されたダイヤモンド)のメーカーをつくることです。博士前期課程1年の時に、ダイヤモンドの結晶成長技術を活かしたベンチャー企業を立ち上げており、宝石としての美しさと、高性能な半導体デバイスという両面の価値を具現化することを目指しています。海外では、宝石事業の利益を産業用アプリケーションの研究開発に還元するモデルが確立されていますが、日本ではそのような企業はありません。私はこのモデルを日本でも実現したいと考えています。そして、日本から世界に通用する技術と製品を発信し、外貨を獲得することで、日本をもっと豊かにしたい。それが私の夢です。研究者としての道と起業家としての道、どちらも魅力的で、今も模索しながら進んでいます。
※所属・学年・年次などはすべて取材当時のものです。ご了承ください。
(サイエンスライター・見寺 祐子)







 PAGE TOP
PAGE TOP